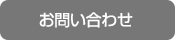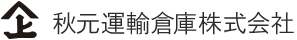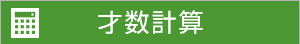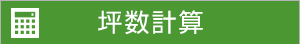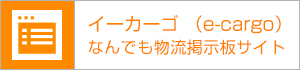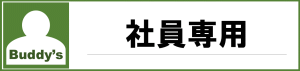さて、いきなりですが…
とても刺激的(…?)な写真を、まずご紹介します。
この写真は、昭和32年(1957年)の梅田駅(大阪)における貨物ターミナルの様子です。
物流に携わる私たちからすると…、恐怖を感じるような光景です。
もちろん、荷物を送った人からしても、「えっ!、私の荷物、こんな扱いをされているの…?」と思うでしょう。
この悪夢のような(とあえて申し上げましょう)貨物の山から、求める貨物を探し出す行為を、当時は「宝探し」と呼んでいたんだとか。
約半世紀が経過した現在、もちろんこんな風景は、国内物流事業者のどの営業所でも、物流センターでもありえません。そして、私たちが、この写真を見て、「これはありえんだろう??」と感じるようになるまでに、物流の品質が向上してきた背景には、先人たちの多大な努力と功績があります。
今回の秋元通信は、「おとなの社会科見学」と称し、当社営業の小島と、芝浦営業所事務の亀田が、クロネコヤマトミュージアムと物流博物館を見学します。
クロネコヤマトミュージアム──経済史に名を残す、ふたりの優秀な経営者の足跡をたどる
ヤマトグループ歴史館 クロネコヤマトミュージアムは、ヤマトグループ創業100周年を記念して設立された施設です。
場所は、品川駅港南口から徒歩10分ほど。
「確か、ここって昔はヤマト運輸さんの営業所だったよね?」と記憶している人もいるかも知れません。今回、アテンドしてくださった担当者にお聞きしたところ、現在も営業所機能を備えているとのこと。
来館者は、6階から3階まで、らせん状に下りながら見学しますが、実はこの上下に車路があるそうです。
今回、一行は90分のアテンドツアーを申し込みました。
今だから言ってしまうと…、「90分って、長いかな?」と思っていたのですが。
あっという間の90分で、むしろ時間オーバーしてしまいました。
詳しい展示内容は、クロネコヤマトミュージアムWebサイトをご覧いただくとして。
きっと、「要は、ヤマト運輸の宣伝施設でしょ?」と思う人もいるかもしれません。しかし、それはとても大きな間違いであり、誤った思い込みです。
1919年に、わずかトラック4台、従業員15名で創業した大和運輸(※当時の表記)の歴史を通して、近代物流発展の歴史を学ぶことができる施設が、このクロネコヤマトミュージアムです。
もうひとつ、注目すべきは、ビジネスを学ぶ場としての、クロネコヤマトミュージアムの価値です。
当時30歳だった小倉康臣氏は、近代化に伴い牛馬車の通行が規制された銀座において、大和運輸を起業します。
「これから貨物輸送の主役はトラックになる」という、小倉康臣氏の読みが見事に当たったことを、現代の私たちは知っています。
その後、1923年には三越をクライアントとして、定期輸送を開始。
1929年には、日本初となる路線事業の定期便を開始し、1935年には関東一円の定期便網を完成させます。
これだけ先見の明を備えた小倉康臣氏ですが、「箱根の山の向こうにはお化けがいるから越えてはいけない」と言い、関東圏の営業にこだわったことから、ヤマト運輸は競合他社に水を開けられ、経営の危機に陥ります。
この危機から会社を救い、物流業界のみならず、日本を代表する大企業へとヤマト運輸を躍進させたのが、小倉康臣氏の次男であり、宅急便を創り上げた小倉昌男氏です。
このあたりのエピソードって、誰かドラマにしてくれないですかね?
特に、小倉昌男氏が社内の反対を押し切って、宅急便をビジネス化した経緯なんて、ワクワクします。小倉昌男氏のキャスティングは、ぜひ堺雅人さんか、阿部寛さんあたりで…、なんて妄想をしてしまうくらい、小倉康臣氏、小倉昌男氏の父子が紡いだビジネスストーリーは、秀逸です。
もちろん、クロネコヤマトミュージアムで展示されているのは「物流」なのですが、この根幹を流れるストーリー、そして得られる学びは、すべてのビジネスパーソンに役立つはずです。
物流従事者はもちろん、ビジネスを学ぼうとするすべての人にオススメしたい、クロネコヤマトミュージアムです。
※画像はクリックで拡大します。またキーボードの矢印キー(← / →)で遷移します。
- クロネコヤマトミュージアムの入り口
- 創業当時の制服だそうです(写真提供:クロネコヤマトミュージアム)
- かつてヤマト運輸が経営の危機に直面したことなど、知らない人も多いでしょうね(写真提供:クロネコヤマトミュージアム)
- 小倉昌男氏が牛丼のビジネスモデルから何を学び取ったのか、詳細は、皆さまの目でご確認ください(写真提供:クロネコヤマトミュージアム)
- ここからは撮影可能エリアです。(左が亀田。右が小島)
- ヤマト運輸の制服を着て、記念撮影ができるコーナーは、子どもに大人気だそうです。
- トラックを見学できることに、小島と亀田もテンションが上がっていました。
- 現場で使われている資材や…
- 亀田が関心を示したのが、ヤマト運輸オリジナルの包装資材。これは「FLIX(フリックス)」という、空気を抜くことで荷物の形状やサイズにフィットするアイテム。
物流博物館──日本の物流史を学び、”今”の物流を見つめなおす
品川駅高輪口から徒歩10分。クロネコヤマトミュージアムとは、品川駅を挟んで反対側に、物流博物館はあります。
物流博物館では、入館料200円を支払って入館します。(クロネコヤマトミュージアムは無料)
こちらでも、あらかじめアテンドのお願いをしておきました。
まずは「暮らしと産業を支える物流」という動画を拝見した後、レクチャーを受けますが…
驚くのは、学芸員の方の博識さです。
「物流」という言葉が生まれた経緯から、冒頭に挙げた梅田駅での宝探しの様子。
また、中世期から江戸時代の物流に至るまで、お話のすべてが学びです。小島、亀田も、真剣にメモしていました。
これだけ、系統的に物流を学ぶことができる施設は、ちょっと他では考えられないのではないでしょうか。
「宝探し」画像の他にも、ここには貴重な資料がたくさんあります。例えば…
※画像はクリックで拡大します。またキーボードの矢印キー(← / →)で遷移します。
これ、今やったら絶対に怒られるやつです。
と言うか、現代の私たちの感覚だと、怖くてこんなこと絶対にやれませんよ…
また、天秤棒を担ぐ体験もできます。さっそく小島が体験しますが…
- 間違ったやり方。これでは揺れる荷物を安定させることができません。
- 正しくは、天秤棒に腕を絡ませるように持つのですが、肩関節がよほど柔らかくないと、腕が回りません。
- このように、進行方向に対し、平行に担ぐやり方もありました。
天秤棒の正しい担ぎ方は、天秤棒に腕を絡ませるようにするのですが。小島は、「肩関節がかたくて腕が回りません」と言っていましたが、これ、よほど肩関節が柔らかくないと、無理なんじゃないでしょうか?
他にも、さまざまな人力による荷役(頭上運搬など)の様子が展示されています。
これらを見ていると、フォークリフトやクレーンなど、マテハン機器の発展が、いかにありがたいものであったかがよく理解できます。
館内では、ジオラマも使い、物流発展の歴史をわかりやすく学ぶことができます。
- 品川宿・問屋場(といやば)の模型。今でいうところの中継輸送拠点です。
- 飛脚(幕府の公用飛脚)です。
- 本馬(ほんま)と呼ばれた荷物輸送専門の馬。約150kgの荷物を運ぶことができたそうです。
- 新橋停車場の荷物積卸場。
- 新発田駅(新潟県)、昭和30年代前半の貨物上屋を再現した模型。
- 一人の馬方が数匹の馬を追い、中継なしで直行して輸送する「中馬(ちゅうま)」。ちなみに、馬は道を覚えてくれるらしく、「いわば自動運転なんですよ」という学芸員の説明に、妙に納得してしまいました。
- もちろん、現在の物流も学ぶことができます。
「こうやって学ぶと、荷役って、海上コンテナやパレットが普及した1950~1960年代までは発展しましたけど、その後、基本的には進化していないんですね…」、小島がつぶやきました。
倉庫作業員を経て営業となった今、彼は俯瞰して現場を見ることができる立場にあります。だからこその感想なのでしょうね。
物流博物館では、(繰り返しになりますが)系統的に物流を学ぶことができます。
ただし、得られる学びは、当人が備えている物流リテラシーに大きく依存するでしょう。その意味では、新人~ベテランを問わず学びを得られる施設ですし、また何度も学びに来るべき施設と言えるでしょう。
小島と亀田は何を感じたのか
- 亀田
クロネコヤマトミュージアムは、単純に「いいなぁ、すごいなぁ」と思いました。
ビジネスとしての知的好奇心がかき立てられました。
新たな取り組みとして紹介されていた、空飛ぶトラックとか、実際に見てみたいです。
物流博物館では、「昔って大変だったんだなぁ。今は恵まれているなぁ」と感じました。
技術の発展とか、ありがたいですね。
知らないことがたくさんあって、今日はとても楽しかったです。
- 小島
クロネコヤマトミュージアムでは、ビジネスの上流に関わること(≒ビジネスを創る立場であること)の大切さを、あらためて感じました。
宅急便を筆頭に、いくつも(当時の)新しいことにチャレンジしていったヤマト運輸のチカラを見せつけられた感じです。
物流博物館では、物流の歴史を学べるということもあって、ガンガン質問をしてしまいました。
興味深かったのは、江戸時代から帰り荷を重要視していたことですね。
今後の仕事でも役立ちそうなヒントをたくさん得ることができた一日でした。
さて「おとなの社会科見学」、いかがでしたでしょうか。
今回ご紹介したふたつの施設が、ともに品川にあるというのは、すごくありがたいです。その気になれば、一日で回れますからね。
繰り返しになりますが、このふたつの施設では、仕事に役立つ、あるいは仕事に対するモチベーションをアップさせてくれるような気付きと学びを得ることができます。まさに「おとなの社会科見学」にうってつけの施設でした。
ぜひ、皆さまも機会を見つけて、訪問してください。
きっと有意義な時間となることでしょう。
両施設のWebサイト
※施設訪問の際には、必ずWebサイトで開館日などをご確認することをオススメします。